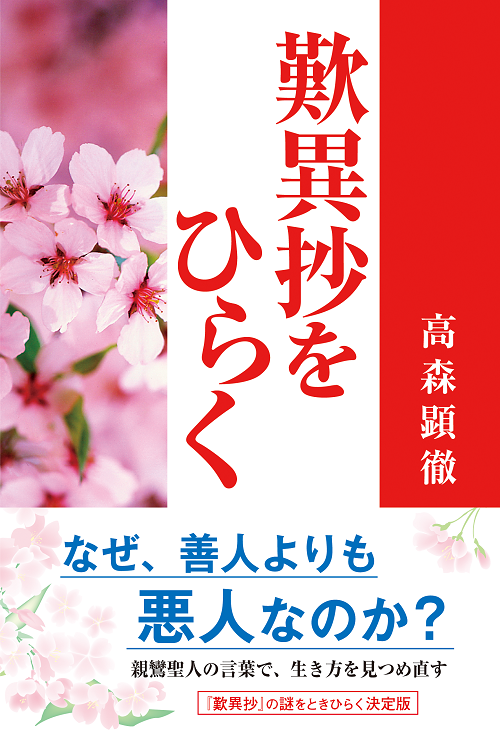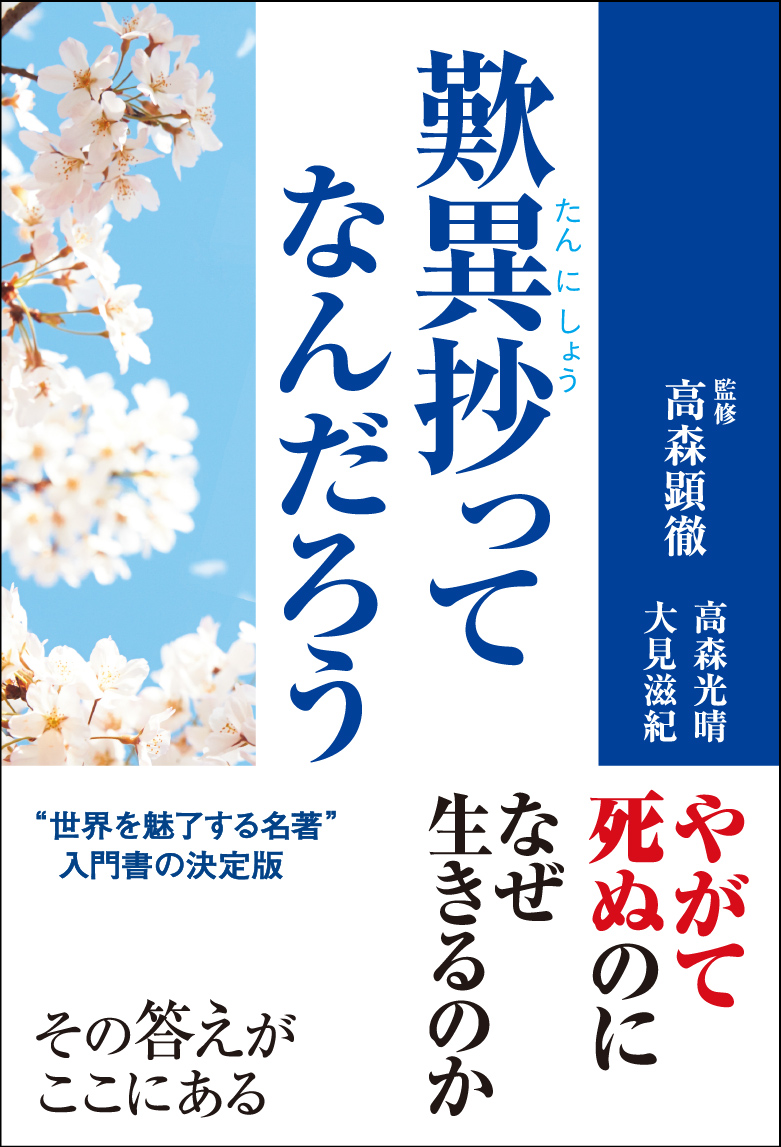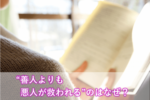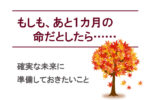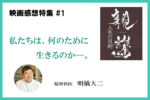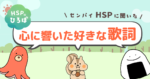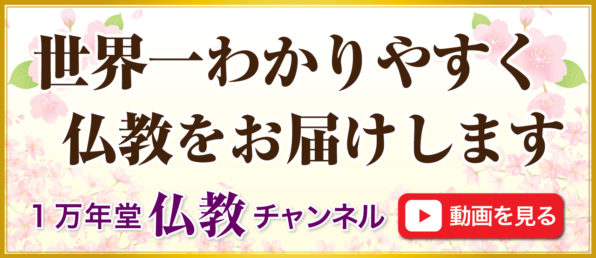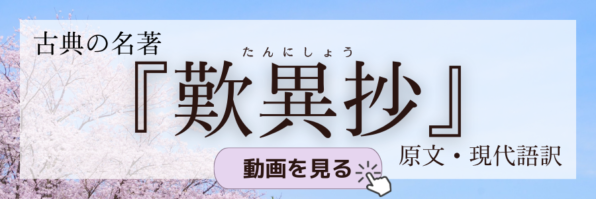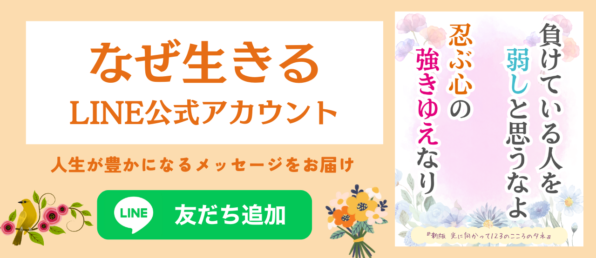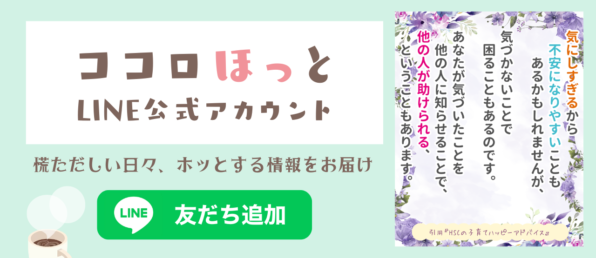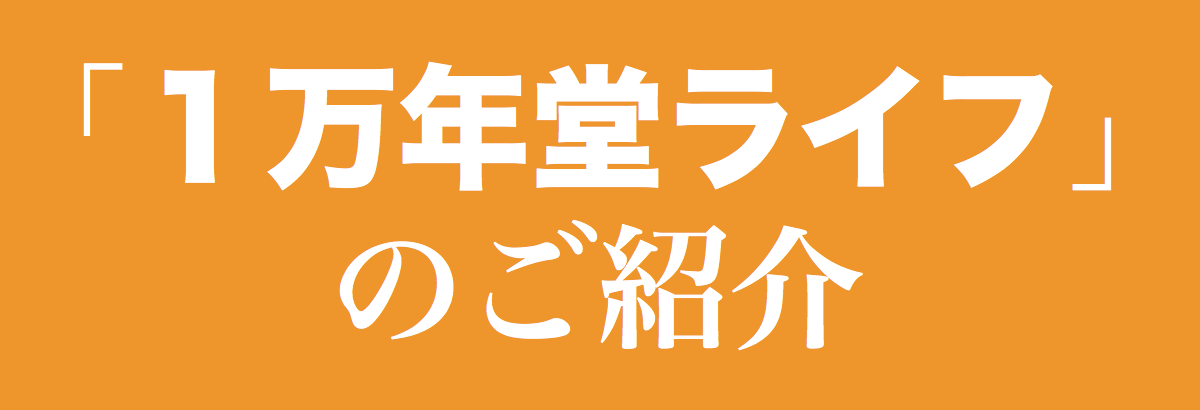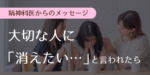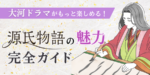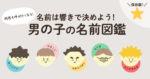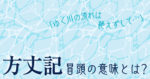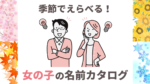『こども歎異抄』とは
子どものころ、ひそかに感じていた、素朴な疑問。
家族や学校の先生に聞いてみても、「そんなものだよ」「考えてもどうしようもない」とごまかされて、モヤモヤした経験はありませんか?
大人になるにつれ、知りたかった気持ちにはフタをして、目の前のことに追われる毎日。
でも、いざ、同じようなことを尋ねられたら……。
今さら聞けない人生の疑問に、ヒントを与えてくれるのが、700年前に書かれた『歎異抄(たんにしょう)』です。
「名前は聞いたことあるけれど、一体どんな本なの?」と思っている方も、多いのではないでしょうか。
日本の文学や哲学、倫理学の糧とされてきた『歎異抄』の内容を、誰もが経験したことのあるエピソードを通じて、マンガ感覚で分かりやすく読める連載が、『こども歎異抄』です。
第1回目は、“ウソにウソを重ねてしまう本当の理由” を考えてみたいと思います。
ウソは、どこからやってくる……?



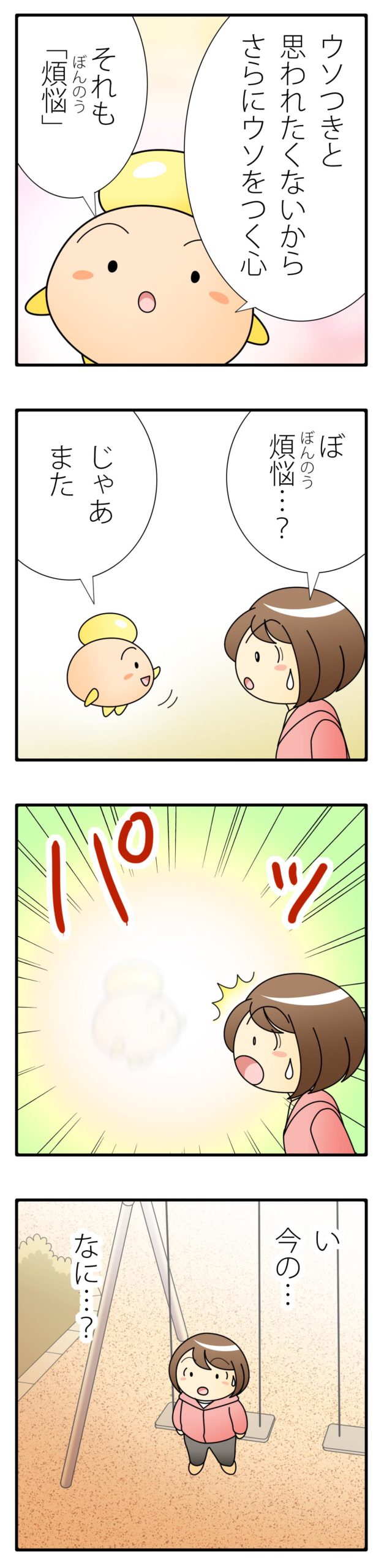
マンガのエピソードのように、子どもがウソをつくと、「どうしてウソなんてつくの!」と、つい頭から叱ってしまうことはありませんか。
ウソでごまかすことを覚えたら、将来、ろくな大人になれないと心配してのことでしょう。
では、ウソをつく子は、特別に“悪い子”なのでしょうか。
ウソをついてしまう、特別に“悪い人間”というのが、存在するのでしょうか。
人間はウソをつく生き物
「私はこれまで、一度もウソをついたことがありません」と言う人はいないですよね。
(もしそんな人がいれば、それがウソということになります)。
やってはならないこと、知られたくないことをしてしまったとき、それを隠そうとして、ウソをついた経験は誰にでもあると思います。
また、子どもだけでなく、大人の私たちはどうでしょう。
むしろ、大人のほうが、世間体を考え、平気で思ってもいないことを口にしているのではないでしょうか。
ウソをついてしまう特別な人間というのが、いるのではありません。
大人も子どもも、どんなに性格が良く見える人も、「ウソをついてしまう心」を持っているのです。
ウソをついてしまう心の正体は?
-

サボりたい心。サボったと知られたくないからウソをつく心。それは『煩悩(ぼんのう)』。
ウソをついてしまう心の正体を、『歎異抄』では、「煩悩(ぼんのう)」と言われています。
煩悩とは文字通り、私たちをわずらわせ、悩ませるものです。どんな人にも百八つあると言われます。
生まれたばかりの赤ちゃんや、いつもニコニコしている恩厚な人を見ると、煩悩が少ないように見えますが、108という数に変わりはありません。
その煩悩の中でも、最初に挙げられるのが、「欲(よく)」の心です。
お金が欲しい、ほめられたい、自分の思い通りにしたい、といった心で、無ければないで欲しい、あればあったで「もっともっと」と無限に広がっていく心です。
この「欲」に5つあり、「五欲(ごよく)」と言われています。
- 食欲(しょくよく)
- 財欲(ざいよく)
- 色欲(しきよく)
- 名誉欲(めいよよく)
- 睡眠欲(すいみんよく)
マンガの中で、子どもが「習い事をサボりたい」と思った心は、「睡眠欲」にあたります。
睡眠というと、夜眠ることを思い浮かべるかもしれませんが、眠たい心はもちろん、サボりたい、なまけたい、楽がしたいと思う心も、「睡眠欲」です。
では、「習い事をサボったと思われたくない」とウソをついてしまう心は、どれにあたるでしょうか。
これは、4つ目の「名誉欲」です。
自分を守るウソを重ねてしまう理由
-

ウソつきと思われたくないから、さらにウソをつく心。それも『煩悩(ぼんのう)』。
自分をよく見せたい、嫌われたくない、という心が「名誉欲」ですから、自分を守るためにウソをつくと、どうなるでしょう?
今度は、「ウソつきな人間だと思われたくない」という名誉欲がでてきます。
そして、さらにウソを重ねてしまうことになります。
そこで厳しく咎められると、「叱られたくない」という思いから、次はもっとしっかりとしたウソを考えるようになります。
「ウソつきは泥棒のはじまり」という諺がありますが、そういった悪循環を教えたものかもしれませんね。
まとめ
相手がウソをつくとき、その背景には、何かしらの理由や、その人なりの心の動きが隠れています。
「ウソをつくのはよくないこと」と伝えると同時に、「なぜそういうウソをつくのか」という背景を理解することが大切です。
また、ウソをついた人を怒ってしまいがちですが、私たちは毎日、近所づきあいや親戚との会話の中で、自分を守るためのウソをついてはいないでしょうか。
どんな人も、朝から晩まで、「人からよく思われたい」「嫌われたくない」という欲の心に振り回されているのです。
自分自身も欲に振り回されていると思えば、目の前の相手がウソをついたときも、何か事情があるのでは、と冷静になれるかもしれません。
このように、「心とは?」「人間とは?」「生きるのは何のため?」を考えるための人生読本が『歎異抄(たんにしょう)』です。
「こども歎異抄」を通して、ぜひ、家族で話し合ってみてくださいね。
(1万年堂ライフ編集部より)