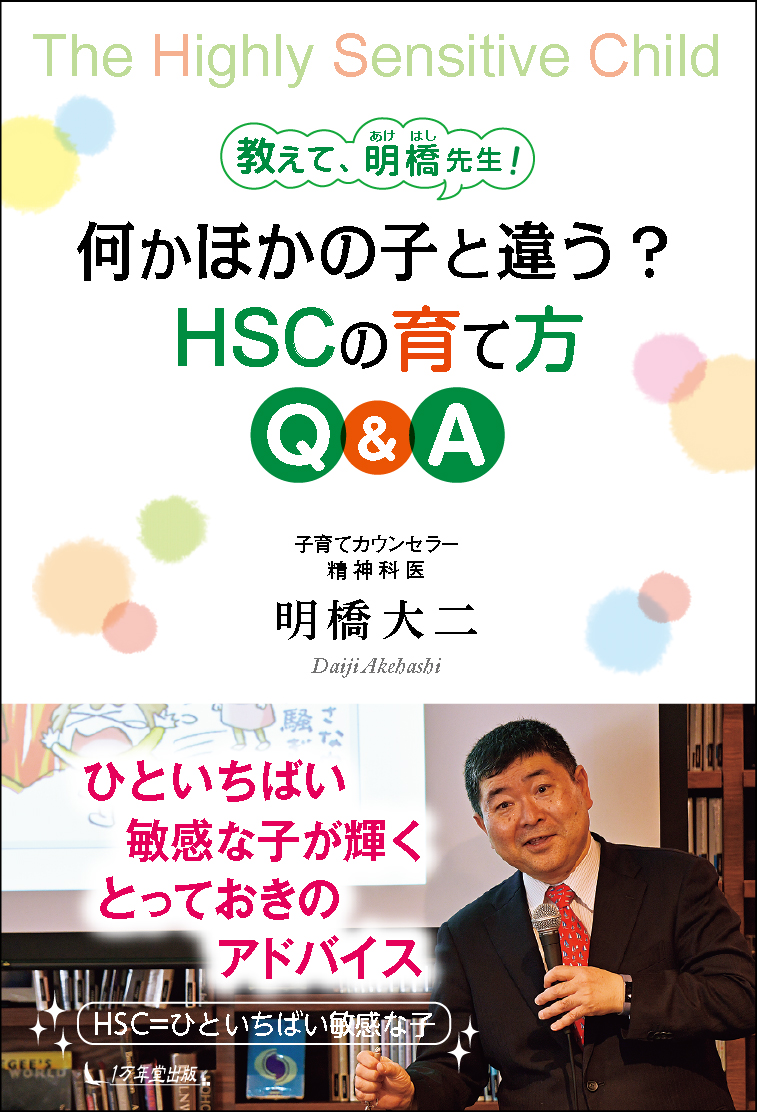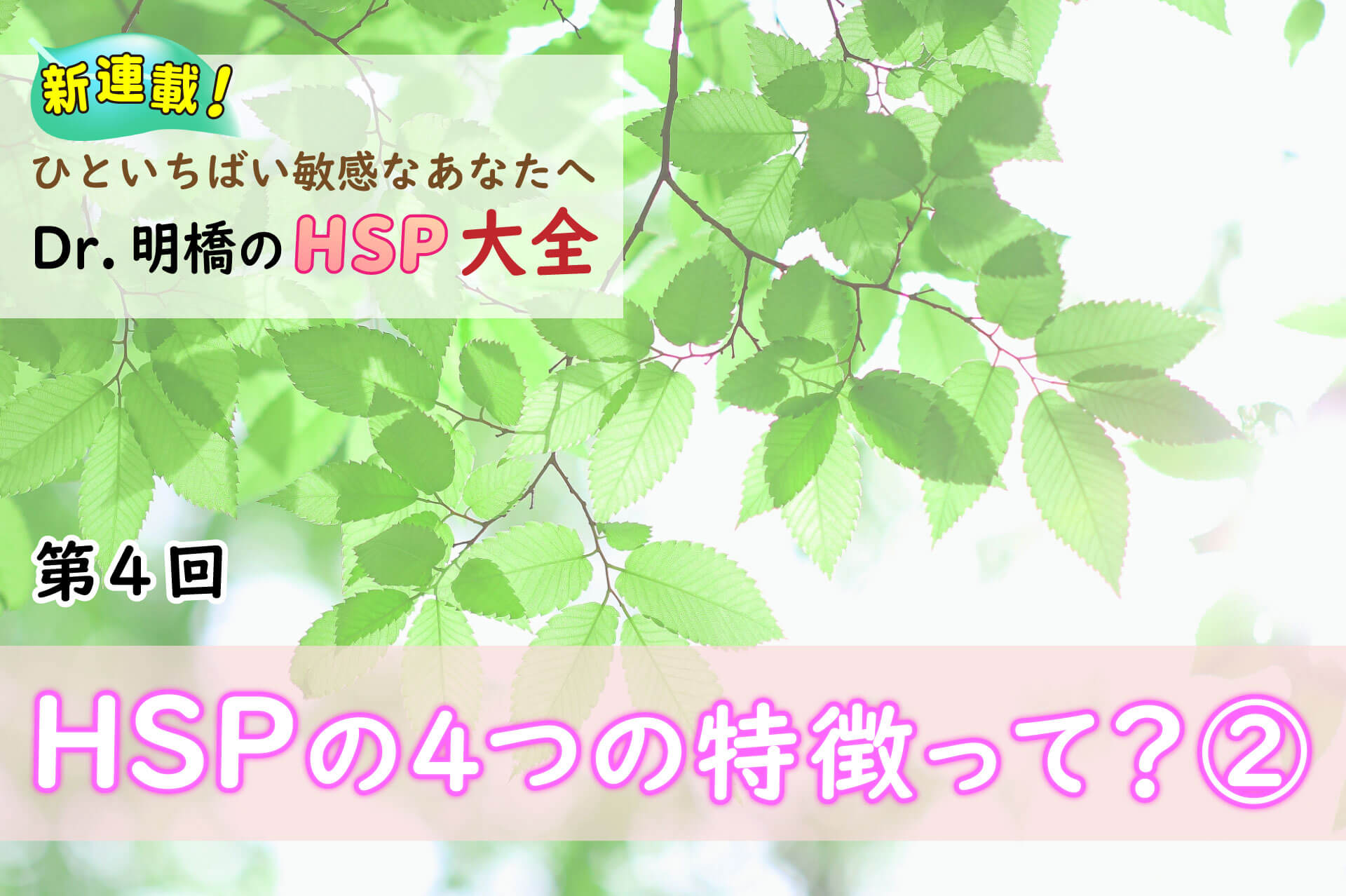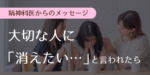HSP(ひといちばい敏感な人)の基本的な知識から、最新の議論までをご紹介する、精神科医・明橋大二先生の連載「HSP大全」第5回です。
人前が苦手、少し怒られただけでもひどく落ち込んでしまう…。
心が弱いから?と思いがちですが、それこそがHSPの大きな特徴の1つ「感情反応の強さ・共感力」かもしれません。
今回は、トラウマ反応との違いや、相手の感情に巻き込まれないための対処法を教えていただきます。
(1万年堂ライフ編集部より)
HSPの基本的な内容は下記でまとめていますのでご覧ください。
つい感情が激しく出てしまうのはHSP?それともトラウマ反応?
DOESの3つめは、感情反応(emotional response)、共感(empathy)の“E”です。
感情反応が強く、共感力の高いHSPは、自分の感情にも他人の感情にも敏感です。
嬉しい、恥ずかしい、申し訳なく思っている、軽蔑している、同情している、感謝している、見捨てられるのではないかと不安でいる……。
そういう気持ちに自分で気づいたり、強いと顔に現れて他人に伝わったりもします。
しかし、それが、生まれつきHSPだからなのか、過去のつらい出来事が原因になっている(一種のトラウマ反応)からかは、判別が難しいです。
HSPとそうでない場合との違いは、感情の反応が起きるのが「あらゆる」場面であるかどうかです。
人は1日の中で数えきれないほど心が動きますが、HSPならいつも心が揺さぶられ、それを意識させられてきたでしょう。
逆に、トラウマ反応であるなら、多くの場合、特定の状況や相手に対して敏感になりますが、生活場面すべてにおいて敏感、ということではありません。
またトラウマ反応の場合、その敏感さはほとんどすべて不快な感情(不安、恐怖、嫌悪)としてあらわれますが、HSPの場合は、もちろん不快な感情もありますが、それだけではなく、感動や喜び、感謝などのポジティブな感情も強くあらわれるところが異なります。
具体的な特徴をいかにいくつか挙げますので、自分もそうだと感じられれば、ボタンにチェックしてください。
半分以上に該当すれば、4つの特徴のうち、Eに当てはまるかもしれません。
※下のフォームから、ぜひ回答をお寄せください。
“E”の具体例
豊かな感情をありのままに出す人は、むしろ愛されます
自分の感情に敏感であることは、自分らしさを大切にできる才能がある、ということなのですが、HSP(特に男性)の中には、小さい頃、誰かの前で泣いて幼稚園の先生や親に怒られたために、泣くこと、感情を自由に表現することをやめてしまった人もいます。
感情をありのままに出すことは恥ずかしいこと、怖いことと思って、心に蓋をしていると、やがて感情があることそのものを悪いことと思うようになり、自分の心が分からなくなってしまいます。
しかし豊かな感情を持つ人は、男女関係なく魅力的です。
人に言えないような怒りの気持ちも、溜めずに出してしまえば、実はたいしたことはないと安心できるものです。
涙もろい人は、むしろ人から愛されます。
多くの人は、強い想いがあると衝動的に行動しがちですが、HSPは、例えば結婚や転職を心に決めていても、行動は慎重です。
ですから感情がコントロールできないのではないかと、心配したり恐れたりする必要はないのです。
他人の感情に敏感であることは、HSPの優しさであり、処世術でもあります。
HSP(特に女性)は、仕事を頑張る夫や心に傷を負う誰かに寄り添ったり、経営者をサポートしたりすることに抜群の才能があります。
空気を読み、適切なタイミングでコメントしたり行動を起したりすることができます。
影響の受けやすさを知って、自分を守るための境界線を
ただ、相手からの影響を受け過ぎて際限なく尽くしてしまう、相手のケアに心を奪われて自分のケアを忘れてしまうこともあります。
相手に指示されたわけでなく、自分が気づいて行動したのに、後になって、相手に搾取されたと怒ることもあります。
自分は自分、相手は相手です。自立した自分があって、誰の要求にどこまで応じるかを自分で決める境界線が必要です。
他人を守る才能を、自分を守るために、もっと使っていいのです。

【ぜひ読んでいただきたい書籍】