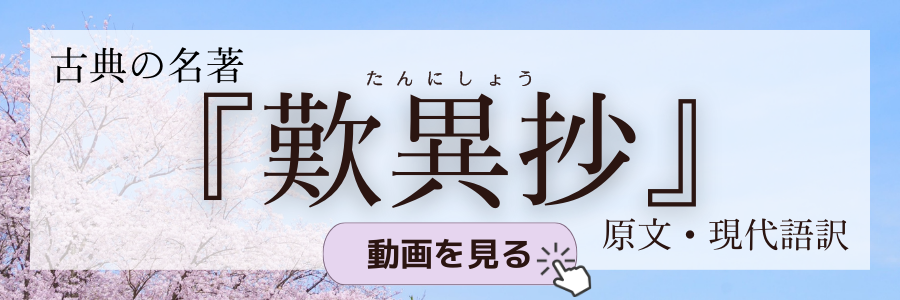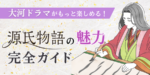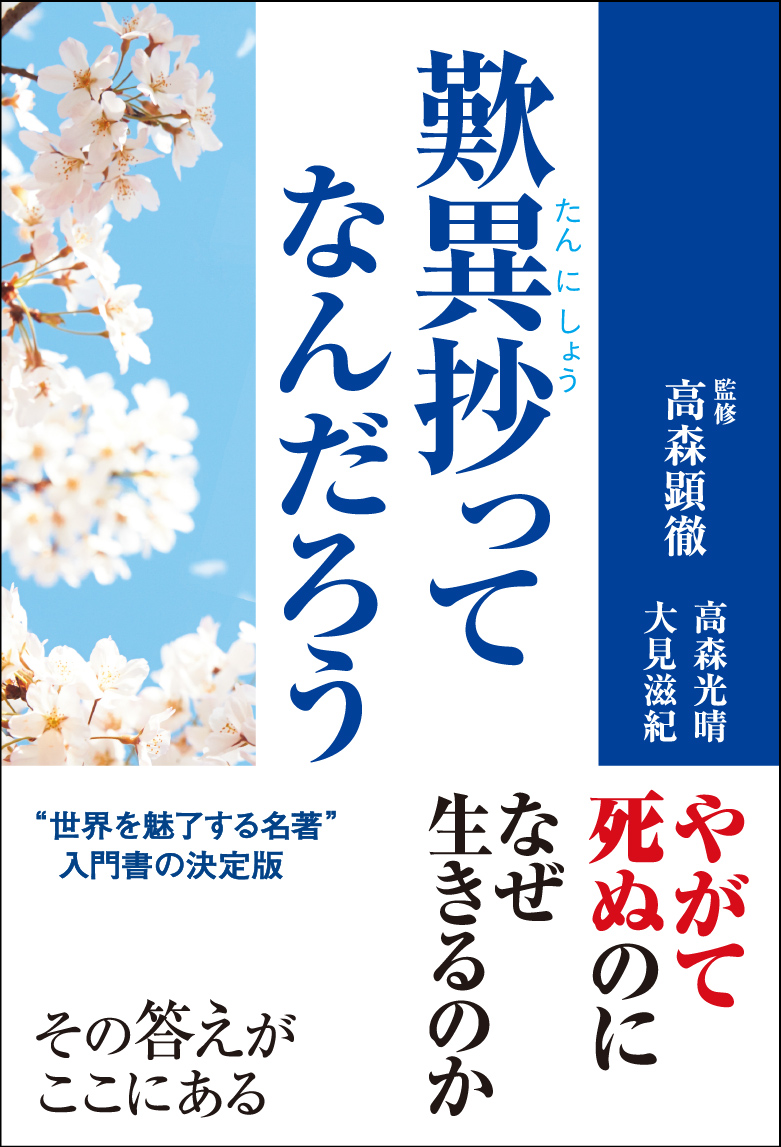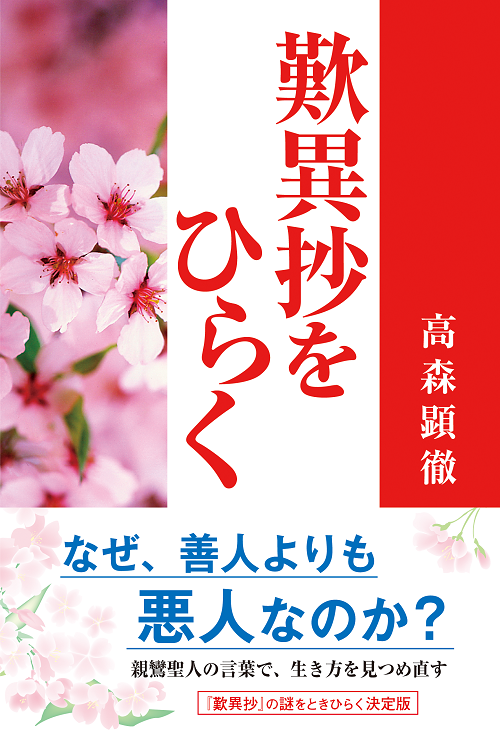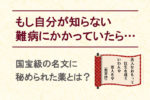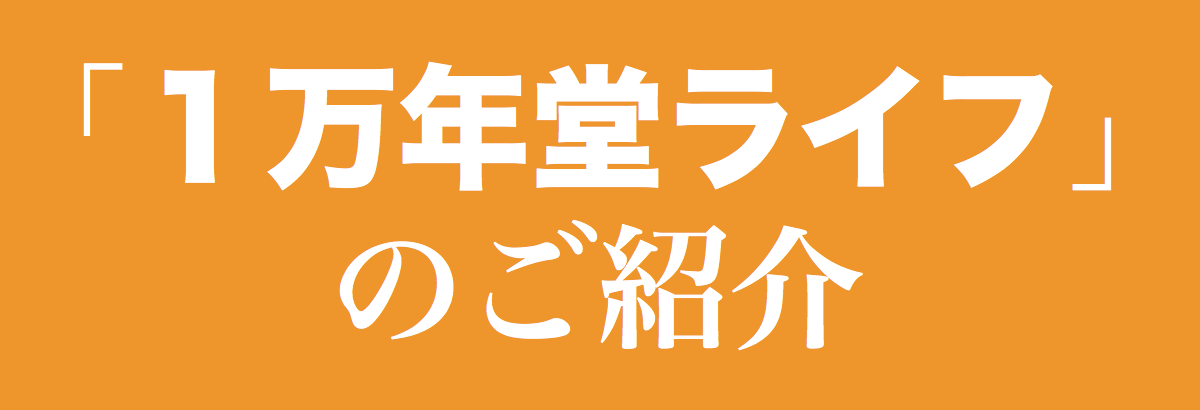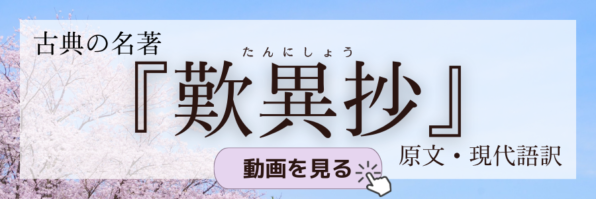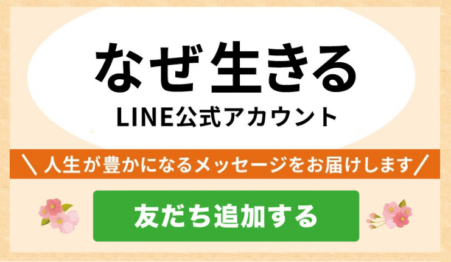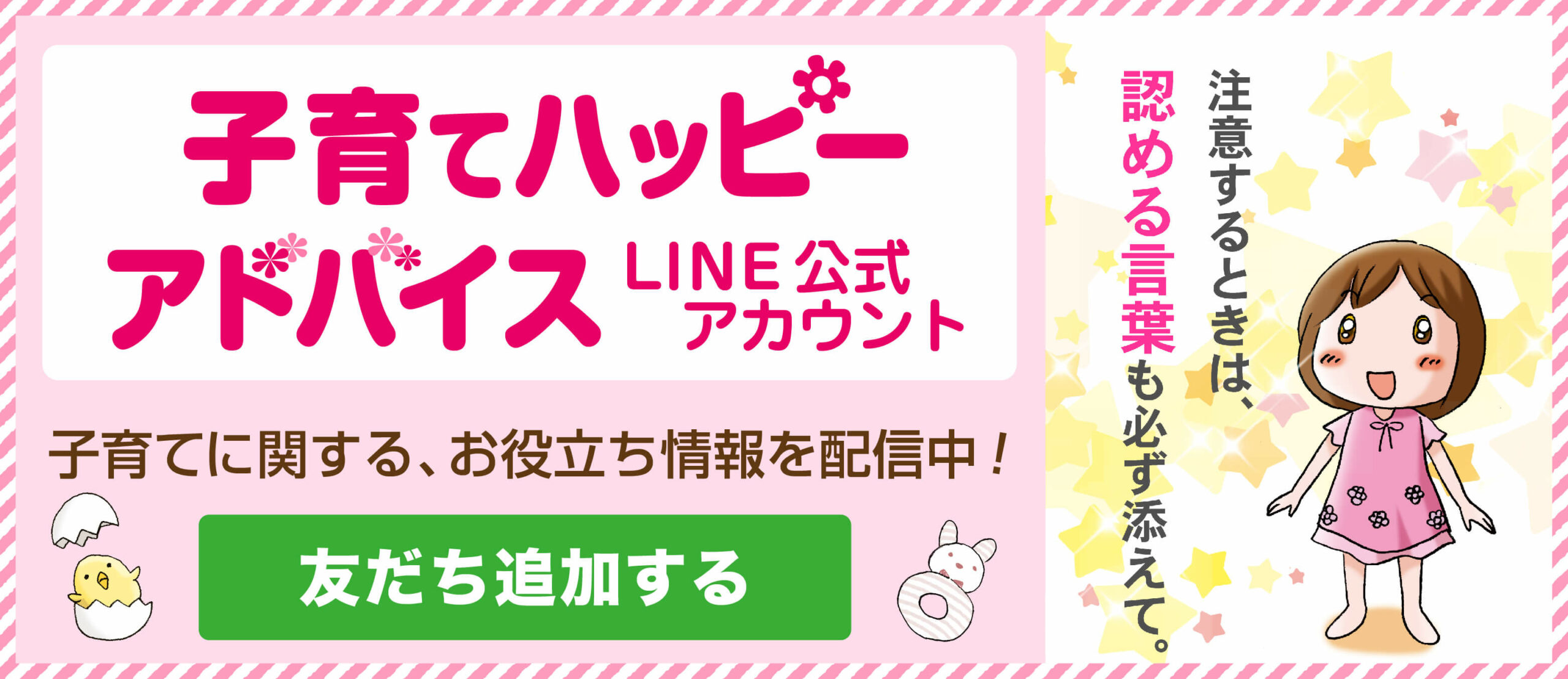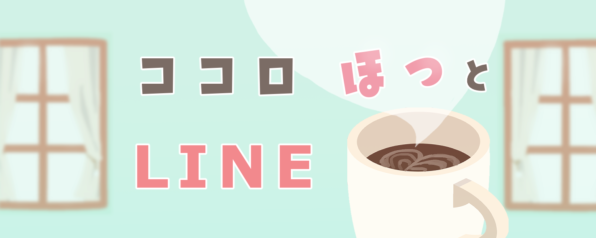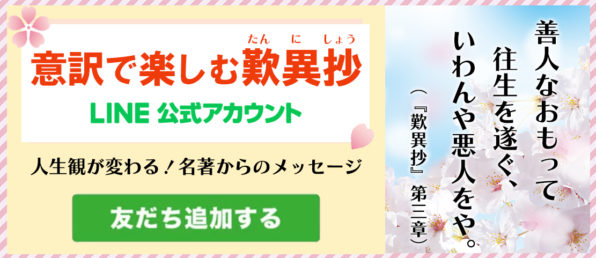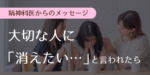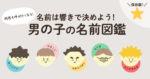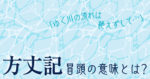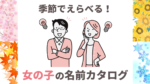こんにちは。国語教師の常田です。
今回紹介する女性、朝顔の姫君にように、「独りで生きていく」と考える女性は、昔もあったのですね。
「朝顔の巻」のあらすじを解説します。
朝顔の姫君からの一言がほしい
30歳を過ぎた光源氏は、身近な人を相次いで亡くしています。
亡き正妻(葵の上)の父、生涯恋慕した継母・藤壺に続いて、叔父の式部卿宮(しきぶのきょうのみや)も世を去りました。
式部卿宮には朝顔の姫君という娘がいました。
実は、10代の時から源氏は、この朝顔にも恋心を訴えてきたのです。
しかし、彼女が応ずることなく、十数年の歳月が経っていました。
父の喪に服する朝顔は、叔母(父の妹)と暮らし始めました。
以前より彼女に近づきやすくなり、源氏はかつての恋心を再び燃え上がらせました。
老いた叔母の見舞いにかこつけて、しきりと朝顔の住む邸に通います。
中年の源氏が、年齢不相応な若々しさをよみがえらせていました。
しかし、やはりというべきか、朝顔の姫君は以前にましてかたくなで、求愛を受け入れようとしません。
源氏は拒まれれば拒まれるほど、思いがつのります。
しびれを切らし、たいそう真剣な面持ちで朝顔にこう訴えたこともありました。
「一言、憎しなども、人づてならでのたまわせんを、思い絶ゆるふしにもせん」(ただ一言、「嫌いです」と直接言ってもらえたら、あきらめるきっかけにもできるのに!)
それでも朝顔は黙ったままでした。
源氏物語で唯一の女性・朝顔の生き方
世間では、すでに2人の仲がうわさされていました。
あの2人はお似合いだ、朝顔の姫君なら人格も家柄も源氏の正妻にふさわしい…などと。
「空しからんはいよいよ人笑えなるべし。いかにせん」(この恋が成就しなければ、ますます世の物笑いになるに違いない。どうしよう)
と源氏は自分の世間体のためにも焦ります。
今までどんな上流階級の女性も彼になびいてきたのです。
源氏にはそれが当たり前でしたから、朝顔がどこまでも拒絶することは、彼のプライドが許しません。
意地になって、しつこく逢瀬を迫るのでした。
実を言えば、朝顔の姫君も光源氏の心ばえの深さや輝く姿に心引かれていました。
けれども、過去に彼と交際した女性の中には、教養があると評判の人でも、彼に恋い焦がれるあまり、嫉妬で大蛇のようにのたうち回って苦しんだことを知り、「源氏に決して心を許してはならない」と思っていたのです。
光源氏の正妻となれば、いろいろと恵まれた生活になることは分かっていましたが、「なおあるまじく恥ずかし」(やはり、あの女性のように苦しみたくはないわ。恥ずかしいことだもの…)。
独りで生きていく。これが彼女の選んだ生き方でした。
朝顔の生き方に考える「幸せとは?」
女性も社会で働くのが一般的な現代ならともかく、平安時代の女性が独身を貫くには相当な覚悟が要りました。
男性の後ろ楯がなければ、困窮して生活が落ちぶれていくのは明らかでしたから。
独身は寂しいし、生活も苦しい。でも、結婚してもきっと苦しむ…。
かつて紫式部も幸せを夢見て結婚したことでしょう。
ところが、夫の浮気に苦しめられ、しかもわずか3年弱で夫は急死。
精神的に打ちのめされ、人格が変わるほどだったとか。
その後、宮仕えにかすかな希望を持ったものの、周囲には自分をライバル視してくる人が多く、人間関係に悩みます。
引きこもりになったこともあり、名声が高まるほど、嘆きは深まるばかりでため息の毎日でした。
伴侶や地位、才能などの有る無しと、幸せは別問題だと知らされて、紫式部は生きる意味を求めたのでしょう。(カフェで源氏物語①参照)
人物紹介:朝顔
桃園宮の娘で、光源氏のいとこ。
聡明で冷静沈着、自分を決して出さない人。
光源氏を拒み続け、最後まで独身を貫き通した女性。
呼び名の由来は、光源氏から朝顔の花を添えた和歌を送られたことからきている。
「朝顔の姫君」「朝顔の斎院」「槿姫君」「槿斎院」など呼ばれることもある。
朝顔について、詳しくお知りになりたい方はこちらの記事をご覧ください。
源氏物語全体のあらすじはこちら
源氏物語の全体像が知りたいという方は、こちらの記事をお読みください。
話題の古典、『歎異抄』
先の見えない今、「本当に大切なものって、一体何?」という誰もがぶつかる疑問にヒントをくれる古典として、『歎異抄』が注目を集めています。
令和3年12月に発売した入門書、『歎異抄ってなんだろう』は、たちまち話題の本に。
ロングセラー『歎異抄をひらく』と合わせて、読者の皆さんから、「心が軽くなった」「生きる力が湧いてきた」という声が続々と届いています!