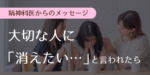古典の名著『歎異抄』ゆかりの地を旅する
NHK大河ドラマ「麒麟(きりん)がくる」第33回は、「比叡山(ひえいざん)に棲(す)む魔物」。
ドラマのクライマックスでは、比叡山が織田信長によって焼き討ちに遭います。当時は、権力と金と比叡山とが結びついていたんですね。
その焼き討ちに遭う約400年前。親鸞聖人(しんらんしょうにん)は比叡山で壮絶な修行の最中、美しい女性と出会います。
その女性から投げかけられた言葉によって、比叡山の仏教への疑問が生じ始め……。
木村さん、よろしくお願いします。
(古典 編集チーム)
![歎異抄の旅⑪[京都・滋賀編] 恋する女性との出会い〜赤山明神の画像1](https://www.10000nen.com/wp-content/uploads/2020/11/tabi011-02.jpg)
「意訳で楽しむ古典シリーズ」の著者・木村耕一が、『歎異抄』ゆかりの地を旅します
(「月刊なぜ生きる」8月号に掲載した内容です)
恋の始まり
美しい女性との出会い……。
それは、若き日の親鸞聖人にとって、激しく、苦しい恋の始まりでした。
「えっ! 比叡山の修行僧が女性に心を奪われるなんて……」
こんな疑問がわくかもしれません。
どんな高僧といわれる人でも、人間である以上は、欲、怒り、恨み、ねたみなどの煩悩を消すことはできません。
親鸞聖人は、偽らず、ごまかさず、自らの心を見つめ、「恋」という名の煩悩と格闘されました。その姿は、多くの伝記、小説、映画に描かれています。
今回は、親鸞聖人が美しい女性と出会われた場所・赤山明神(せきざんみょうじん)を訪ねてみましょう。
京都駅から、電車を乗り継いで、比叡山のふもとへ向かいます。
修学院(しゅうがくいん)駅で下車。無人駅です。
![歎異抄の旅⑪[京都・滋賀編] 恋する女性との出会い〜赤山明神の画像2](https://www.10000nen.com/wp-content/uploads/2020/11/01-3.jpg)
町の中を、比叡山へ向かって10分ほど歩くと音羽川(おとわがわ)にさしかかります。
![歎異抄の旅⑪[京都・滋賀編] 恋する女性との出会い〜赤山明神の画像3](https://www.10000nen.com/wp-content/uploads/2020/11/02-2.jpg)
この川に沿って、上流への道を進んでいくと、多くの人が集まっていました。修学院離宮の庭園を見学に来た観光客です。
その手前を左折して、しばらく歩くと赤山禅院(せきざんぜんいん)が見えてきます。人影もなく、静かな場所でした。
「赤山明神」と刻まれた大きな石碑が立っています。
山門の左の柱には、「赤山禅院」と墨で大書されています。両方の呼び名があります。
![歎異抄の旅⑪[京都・滋賀編] 恋する女性との出会い〜赤山明神の画像4](https://www.10000nen.com/wp-content/uploads/2020/11/03-2.jpg)
門をくぐると、参道は、緩やかな上り坂になっています。道の両側に石垣が積まれ、空を覆うように樹木が茂っていました。
赤山禅院は、紅葉の名所として知られています。秋になると、この参道は、赤や黄色の美しいトンネルに変わるのでしょう。
行者が残した草鞋
参道を進むと、左側の一段と高い所に、いくつもの建物が現れてきます。
境内に受付があったので、尋ねてみました。
「赤山禅院は、比叡山延暦寺(えんりゃくじ)にとって、どういう役割があるのですか」
「千日回峰行(せんにちかいほうぎょう)の道場であり、仏道修行をする者にとって重要な場所です」
千日回峰行とは、比叡山で行われる最も厳しい修行です。行者は約300カ所の定められた場所で礼拝しながら、比叡山の峰から峰へ歩き続けるのです。千日間で歩く距離は、地球を1周する距離と同じだといわれています。
「千日回峰行の行者が、この寺に立ち寄るのですか」
「赤山禅院は、比叡山への登山口・きらら坂の近くにあります。千日回峰行の行者は、きらら坂を下りてきて、ここで草鞋を履き替え、さらに歩き続けるのです。履き古した草鞋は、今も、この裏の建物の軒下につるしてあります」
千日回峰行の行者が残した草鞋を見に行くことにしました。
それは、受付の裏の建物の軒下に、ズラリとつるされていました。
![歎異抄の旅⑪[京都・滋賀編] 恋する女性との出会い〜赤山明神の画像5](https://www.10000nen.com/wp-content/uploads/2020/11/04.jpg)
その数の多さに驚きました。
ボロボロにほつれた草鞋を、じっと見つめていると、白装束に身を包み、峰から峰へ歩き続ける行者の姿が目に浮かんでくるようでした。
![歎異抄の旅⑪[京都・滋賀編] 恋する女性との出会い〜赤山明神の画像6](https://www.10000nen.com/wp-content/uploads/2020/11/05.jpg)
この山には、非情な掟がありました。
「千日回峰行を、途中で断念する場合は自決せよ」と。
たとえ病気になっても、親が危篤と知らせが届いても、中断することは許されませんでした。
どんな覚悟で、ここで草鞋を履き替え、仏道修行に励んだのだろうかと、厳粛な気持ちになりました。
古典『歎異抄』を理解するには
なぜ、仏教を求めるのか。
なぜ、厳しい修行をするのか。
この目的が分からないと、親鸞聖人の生涯も、古典『歎異抄』も理解できなくなります。
幼くして両親を亡くされた親鸞聖人は、
「次に死ぬのは自分の番だ」
と、無常を強く感じられました。
「死んだら、どこへ行くのか」
「死後は、あるのか、ないのか」
えたいの知れない不安と疑問がわいてくるのです。
人は必ず死にます。これらの不安や疑問は、すべての人にとっての大問題です。
この大問題を、仏教では「生死(しょうじ)の一大事」といいます。
「生死の一大事」を解決し、この世から永遠の幸福になるために仏教を求めるのです。
親鸞聖人は、9歳で出家を決意し、比叡山延暦寺の僧侶になられました。
延暦寺は「自力の仏教」です。欲、怒り、恨み、ねたみなどの煩悩を抑えて難行苦行に励むことによって、「生死の一大事」を解決しようとする教えです。
親鸞聖人は、この教えに従い、千日回峰行も成し遂げられたと伝えられています。まさに、煩悩と格闘の日々でした。
「なぜ、女を差別するのですか」
そんなある日、親鸞聖人が、都から比叡山へ戻ろうとして、赤山明神の前を通られた時のことです。
どこからともなく、
「親鸞さま、親鸞さま」
と呼びかける女の声がしました。
「こんな所で、誰だろう?」
振り返ってみると、ハッとするほど美しい女性が立っていました。
「私を呼ばれたのは、そなたですか」
「はい。私でございます。親鸞さまに、ぜひ、お願いがあって……。どうか、お許しください」
「この私に、頼み?」
「はい、親鸞さま。今からどこへ行かれるのでしょうか」
「修行のために、山へ帰るところです」
「それならば、親鸞さま。私には、深い悩みがございます。どうか山にお連れください。この悩みを何とかしとうございます」
「それは無理です。あなたもご存じのとおり、このお山は、伝教大師(でんぎょうだいし)が開かれてより、女人禁制(にょにんきんぜい)の山です。とても、お連れすることはできません」
「親鸞さま。親鸞さままで、そんな悲しいことをおっしゃるのですか。伝教大師ほどの方が『涅槃経(ねはんぎょう)』を読まれたことがなかったのでしょうか」
「えっ、『涅槃経』?」
「はい。『涅槃経』の中には、『山川草木悉有仏性(さんせんそうもくしつうぶっしょう)』と説かれていると聞いております。すべてのものに仏性があると、お釈迦さまは、おっしゃっているではありませんか。それなのに、このお山の仏教は、なぜ女を差別するのでしょうか」
「……」
「親鸞さま。女が汚(けが)れているから、と言われるのなら、汚れている、罪の重い者ほど、余計に哀れみたまうのが、仏さまの慈悲と聞いております。なぜ、このお山の仏教は女を見捨てられるのでしょうか」
鋭い指摘に、親鸞聖人は、返す言葉がありませんでした。
今でこそ比叡山は、観光バスや自家用車、ケーブルカーなどで、誰でも登ることができます。どの寺へ参拝するのも自由です。
しかし、明治時代までは、「女人禁制」「女人結界の地」として、女性の入山は固く禁じられていました。
老苦、病苦にさいなまれ、やがて死んでいくのは、男も女も同じです。
「死んだらどうなるのか」と、真っ暗な心に苦しんでいるのは、男だけではないのです。
それなのに、なぜ、比叡山の仏教は、女性を差別するのか……。
赤山明神に現れた女性の言葉は、親鸞聖人の胸に深く突き刺さるのでした。
すべての人が平等に
やがて女性は、
「親鸞さま。どうか、すべての人が平等に救われる教えを明らかにしてくださいませ」
と言い残し、どこへともなく去っていきました。
「欲にまみれ、怒り、恨み、ねたみの心が渦巻いている人間は、救われないのか」
「男も女も差別なく、平等に救われる教えはないのか」
この疑問が氷解するのは、親鸞聖人、29歳の時です。
法然上人(ほうねんしょうにん)から、阿弥陀仏(あみだぶつ)の本願を聞かせていただくまで、煩悩との格闘は、まだまだ続くのでした。
『歎異抄』には、阿弥陀仏の本願に救い摂られた親鸞聖人の言葉が、次のように記されています。
(原文)
弥陀の本願には老少善悪の人をえらばず、ただ信心を要(よう)とすと知るべし。
そのゆえは、罪悪深重(ざいあくじんじゅう)・煩悩熾盛(ぼんのうしじょう)の衆生(しゅじょう)を助けんがための願にてまします。
(『歎異抄』第1章)
(意訳)
弥陀の救いには、老いも若きも善人も悪人も、一切差別はない。ただ「仏願に疑心あることなし」の信心を肝要と知らねばならぬ。
なぜ悪人でも、本願を信ずるひとつで救われるのかといえば、煩悩の激しい最も罪の重い極悪人を助けるために建てられたのが、阿弥陀仏の本願の真骨頂だからである。
![歎異抄の旅⑪[京都・滋賀編] 恋する女性との出会い〜赤山明神の画像7](https://www.10000nen.com/wp-content/uploads/2020/11/00.jpg)
(イラスト 黒澤葵)
現代も、パワハラやセクハラや、人種問題など、さまざまな差別で苦しんでいます。すべての人が平等にとは、『歎異抄』の言葉は深いですね。次回もお楽しみに。(古典 編集チーム) 意訳で楽しむ古典シリーズ 記事一覧はこちら