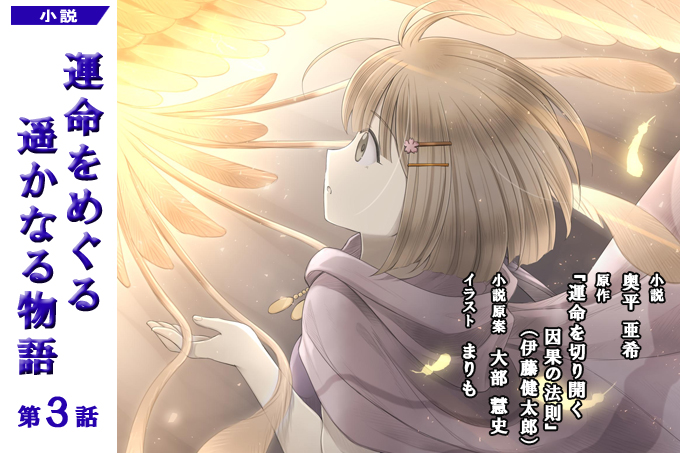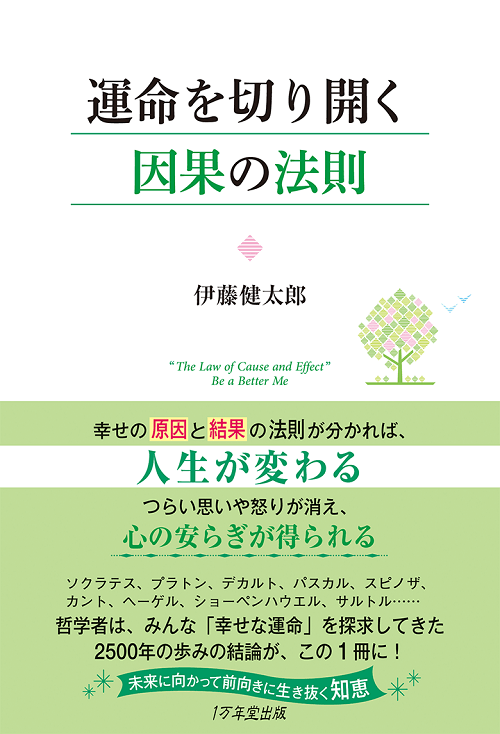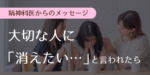前回までのあらすじ
第1話「貧しい国」は、どんな悪いことをしてもすべて金で解決できる「心の貧しい人たち」の住まう国だった。
第2話「科学の国」は「人間は物質の塊にすぎない」と信じている国。
死んだら無になるのだから、善をしようと悪をしようと来世に報いはないのか?
理性と感性をフル回転させ、自分自身の答えを掴んでいく知子。
そして2人が3番目に向かったのは、その名も恐ろしい「呪われた国」だった―。
第3話 呪われた国編
『おはよう、知子。もうご飯できるわよ』
いつもと変わらぬ朝、知子の母親が台所で働いている。
すでにテーブルにはトーストにハムエッグ、サラダにコーンスープが並んでいた。
急いで顔を洗い『いただきます』と手を合わせると母親はにっこりと微笑んだ。
いつもと変わらぬ朝、母の姿がここにある。
『運命は自分の行いが作り出すのさ。だから悪いことはやめて善いことをしなければならないんだ』
なぜか、ソラの言葉がどこからか聞こえてきた。
知子にとって、ソラは頼れる旅の案内人であり友人だ。
だが、その力強い言葉は、ときに知子の心を傷つける。
『悪い行為には悪い運命がおとずれるものさ』
いつか聞いたソラの言葉だ。
間違ってはいないと思う。
だけど、納得できるものでもない。
(お母さんは悪い人じゃない!悪いことなんかしてない!)
知子は反論したかった。だが、なぜか声がでない。
(もっと悪い人はいくらでもいるじゃない!なんでお母さんなの!?)
母親の姿が遠ざかる。知子が「待って」と声をかけたが、ガタガタとうるさい音にかき消されてしまった。
「お母さん!!」
ガタリ、なにかが揺れた。
見慣れぬ空間に激しい振動。目の前には母ではなくソラがいた。
「トモ、うなされてたみたいだけど大丈夫かい?」
ソラの言葉で徐々に自分のいる場所が分かってきた。
ここは次の国へ向かう馬車のなか、もう馬車に揺られて2日目になる。
馬車の旅といえば優雅なイメージを抱いていたが、そんな知子の幻想を砕く乗り心地だ。
なにせこの馬車にはサスペンションもゴムタイヤもないのである。
騒音と振動は絶え間なく知子をさいなみ、身も心も疲れきっていた。
「くたびれたろう?でも、暗くなるころには到着だ」
知子は安堵の息を吐いた。もう根をあげたくなっていたのだ。
「よかった。次はどんな国なの?」
「呪われた国」
その言葉に知子は思わず眉をひそめた。
貧しい国よりさらにひどそうだ。
「大丈夫だよ。治安もいいし、石畳のきれいな町さ」
「ならなんで―」
その時、頭上からの眩い光に馬車が包まれた。
(わっ、UFO?)
手をかざして指の隙間から見た『それ』は信じられないことに鳥だった。
尾が驚くほど長く、神輿のてっぺんに乗ってそうなフォルムをしている。
「あれは知恵の鳥だ。闇夜を昼に変えると聞いていたが比喩ではなく本当に輝くんだね。アタシも見るのは初めてさ」
「すごい鳥だね。なんで光るんだろ?」
知子の言葉にソラは肩をすくめ「わからないのさ」と笑った。
「どこに生息しているのか、何を食べるのか、生態は一切不明。数年に一度ああやって飛んでいるのを見かけるらしいね。運がよかった」
信じられない世界だ。あんなのが日本にいたら大騒ぎになるに違いない。
◆◆◆◆◆◆◆
しばらく余韻にひたっていると、ゆれが治まってきたようだ。
さきほどまでガタガタだった道が舗装されている。
目的地についたようだ。
きれいな石畳と赤いレンガの美しい町、旗やレリーフに描かれているのは知恵の鳥だろう。特徴的な尾でそれとわかる。
「もう日暮れだ。町を見るのは明日にして宿を探そう」
慣れた様子のソラに続いて町を歩くと、広いスペースが見えた。なにやら人だかりができているようだ。
(広場?違うな、お墓かな?)
よく見れば背の低い石が規則正しく並んでいる。知子の知るデザインではないが墓石だろう。
人だかりのなかではスーツを着たエリートサラリーマンみたいな人が演説(?)をしているようだ。
「悲しむことはありません。カレス様はおっしゃいました『この世のすべての結果、人の運命は既に決まっているのだ』と。運命は変えられるものではなく、定められた役目を終えた故人が―」
ぼんやりと眺めていると聞いたような名前が出てきた。
(またカレスさん?科学の国でも聞いたような…)
知子が首をかしげると、ソラが「あれはこの国の葬儀さ」と教えてくれた。
耳をすませば「こんな子供がねえ」「運命だと諦めるしかない」などと嘆きの声が聞こえた。
(子どもが亡くなったんだ)
遺族の嘆きぶりを直視できず、知子は目をそむけてしまった。
「カレスさんて色んなところで聞いた気がするね。たしか科学の国と…貧しい国でも聞いたかな?」
「ふん、手広くやってるみたいだね」
知子の問いにソラがいかにも不愉快だと言わんばかりの態度で答える。
(ソラと知り合い?仲が悪いのかな?)
彼女の不快げな様子を見て知子はカレスの話題をやめることにした。
墓地では見たこともない不気味な赤黒い鳥が、ケケケケと笑うように鳴いている。
「血鴉だね。人の不幸を喜ぶ害鳥さ」
たしかに不気味な赤黒い色は血の色を連想させる。名前の由来だろう。
吐き捨てるようなソラの呟きが印象的だった。
◆◆◆◆◆◆◆
幸い、宿はすぐに見つかった。
落ち着いた感じの外観で、知子が想像するホテルよりは小ぢんまりとしている。
「ふーっ、ベッドで寝れるのは嬉しいな」
「はは、馬車は大変だったろう」
二人部屋に簡素なベッドだが、馬車の責め苦とは比べ物にもならない。
知子は倒れこむようにベッドに身を預けた。
「さっきのお葬式…『人の運命は決まってる』って言ってたけど―」
知子は目をつぶり、先ほどの演説を思い出していた。
(運命は変えられるものではない、か…そのほうが諦めがつくかもね)
やはり知子が思い出すのは母のことだ。あの酷い事故も『決まっていた』のだろうか。
「大きな不幸が訪れた時、運命だと諦めて慰めれば確かに一時的には楽になれるかもしれないね。でも、なぜ不幸が訪れたのか、原因を究明しなくちゃ次の不幸を防ぐことができないだろ?」
ソラは一息つき、窓の外を物憂げに眺めた。
窓の外には先ほどの気味の悪い鳥がとまっている。
「重要なのは聞こえのいい慰めじゃない。正しく事実を認識し、本当の原因を解明することさ」
なるほど、ソラらしい意見だと知子は頷いた。
「でも、この国の人々はね、不幸なことが起きるとすべて運命だと諦める。それでは問題の根本解決はできず、まるで呪いのように同じトラブルが続くときがある。だからいつしか『呪われた国』なんて呼ばれ始めたのさ」
さっきのカレスのことがあったからだろうか。
ソラの言葉は徐々に激しさを増し、知子もうんざりし始めた。
今はちょっとつき合える気分ではない。
「運命を引き起こすのはその人の行為だ。不幸はその人の悪い行いが引き起こすのさ、それにね―」
また、この話だ。知子は今朝の夢を、優しかった母親とその死を思い出した。
「聞きたくないよ」
つい、言葉が口から漏れた。
ソラが意外そうな顔をし、理性が『これ以上言っちゃダメ』と警報を鳴らす。だけど溢れ始めた感情が止められない。
「私のお母さんは殺されたんだよ?そんなの、おかしいよ」
ソラはなおも何かを伝えようとしているようだが、聞きたくもない。
知子はそのまま耳をふさぐようにベッドにもぐりこみ、ソラもそれ以上何かを言うことはなかった。
軽い、自身のため息だけが知子の耳に残った。
◆◆◆◆◆◆◆
翌朝、朝も早い時間から知子は一人、街に出た。目的があったわけではない。ただ、昨夜のことを思い出すと腹立たしくてしかたがないのだ。
(運命は自分の行いが作り出す?そんなのおかしいよっ!!お母さんがどんな悪いことしたっていうのよ!?もっと悪い人はいくらでもいる!なのになんでお母さんなの!?お母さんは悪くない!!)
一晩熟成された怒りは治まるどころか濃度が増したらしい。
今はただ、ソラの顔を見たくない。
あてもなく石畳を歩いていると、間近いところでバァンとあとを引く破裂音が鳴り響いた。
(えっ、なに?銃声?)
思わず知子はその場にしゃがみこんでしまう。
ソラに『治安がいい』と言われたのを鵜呑みにしていたが、考えてみればここは知らない土地なのだ。
「おいっ!誰か倒れているぞ!」
「誤射じゃないだろうな!?大丈夫かあんた!」
恐怖に震える知子に声をかけたのは揃いの制服を着た男たちだ。
肩からベルトで鉄砲を吊し、先ほどの血鴉の死骸を手にしている。
「…大丈夫です。すみません、大きな音に驚いちゃって」
知子が身を起こし、なんとか伝えると男たちは「ほっ」とした表情を見せた。
「驚かせてしまったね、旅の人。この国では血鴉が増えすぎていて定期的に駆除をしてるのさ」
「なにせコイツらは鳥のくせに暗くなると人を襲うからな。明るいうちに駆除しないとな」
どうやら今日は町の害鳥駆除の日だったらしい。
男たちは知子を心配して宿まで送り届けてくれたのち、見回りに戻っていった。
◆◆◆◆◆◆◆
(なんか…帰ってきちゃったけど、どうしようかな)
部屋に戻るとソラの姿はなく、書き置きがあった。
そこには知子に謝罪の気持ちと、心配して町へ探しに出る旨が記されている。
知子は置き手紙を取ろうとし、自分が何かを握り込んでいることに気がついた。
見れば石のようなゴツゴツとした何かだ。どうやら道にへたりこんだ時、無意識に拾ったものらしい。
(石じゃないな?なんだろ…ちょっと動いたかも?)
なぜか妙に気になり、その何かを眺めていると、ヒビが入る。
「あ、卵か」
みるみるヒビが大きくなり中から一羽の鳥が産まれた。
産まれたてのヒナには湿った灰色の羽がみすぼらしく張りつき「ぴ、ぴ」と弱々しく鳴いている。
「…お前、可愛くないね」
ハッキリいって、不細工。しかし、知子に向かい必死にくちばしを動かす姿は愛嬌がある。
刷り込みというやつだろうか、知子を親鳥だと思ってるようだ。必死で何かを訴えている。
「うーん、あげるものなんかないなぁ…あ、そうだ。これ食べるかな?」
知子が保存食の堅焼きビスケットを砕いて与えると、ヒナは喜んでついばんだ。
もともと知子は動物好きだ。餌をやるうちにすっかりこのヒナが気に入ってしまった。
「名前をつけてあげようか?」
知子が語りかけると、不細工なヒナは「ぴ、ぴ」と返事をした気がした。
「ぴーちゃん?ぴー子?…うーん、ピコ!」
どんな生き物でも懐けばそれなりに可愛い。まして、このヒナは自分を親鳥だと思っているのだ。
名前をつけたとたん、知子はヒナをぐっと身近に感じた気がした。
湿っていた羽毛も乾いて、ふんわりとしてきたようだ。
「ちょっとだけ、かわいくなった?気のせいかな」

柔らかそうな毛並みに誘われ頬ずりをすると、ピコは応えるように知子の顔をついばんだ。
(そうだ、この子を連れて外に出てみようかな。まだ暗くなるまで時間があるし―)
知子はピコを連れて街に出ることにした。特に用事があるわけではない、ただピコを外に連れ出し、街の人に見せびらかそうとしただけだ。
つい先ほどの銃声のことなど、この素敵なアイデアに比べれば何ほどでもない。意気揚々とドアを開ける。
だが、知子の浮き立つ気持ちとは裏腹に、街の人々の様子がおかしい。
知子とピコを見て眉をひそめ、なにやら小声でささやきあっている。中には露骨に指をさす者までいた。
(なんだろう、この雰囲気…ちょっとおかしい)
知子が不安を感じ始めたとき「ちょっといいかな」と呼び止められた。
見たことのある制服、害鳥駆除をしていた男たちだ。彼らは注意深くピコを観察している。
「間違いない血鴉の幼体だ」
男はぶら下げた鳥の死骸を知子に見せつけるように掲げた。
数珠つなぎになったそれにはピコによく似た姿もある。さすがにこれにはゾッとした。
「その鳥はすぐに人を襲うようになる、こちらに渡しなさい」
男の一人がぬっと手を差し出し、知子はとっさにピコを庇った。
ここで引き渡せばどうなるかくらい知子にも想像はつく。
「この子は私のこと親鳥と思ってるみたいだし―」
「残念だがそういう問題じゃない。この国ではね、クマを我が子だと愛情をもって育てた猟師が食い殺されたこともあるのだよ。血鴉も同じ話さ、わかるだろう?」
知子の手の平では何もわからぬピコが「ぴ、ぴ」と鳴き声を上げた。
とても人を襲うとは思えない。
(そうだ、私はピコの親鳥なんだ。信じてあげなきゃダメ)
知子は意を決し、顔を上げた。
「そんなのおかしいです」
「おかしくない。それは人を襲う害鳥なんだ。運命に定められた役割なんだ」
男の言葉を聞き、知子は「やっぱりおかしい」と再度口にした。
「産まれたばかりのピコが人を襲うと決めつけないでください!産まれながらに全ての運命は決まっているなんておかしいです!」
ピコが殺されるかどうかの瀬戸際なのだ。知子だって黙っているわけにはいかない。
「いいから渡しなさい、これはお嬢さんのためになることなのだから―」
男が再度ピコに手を伸ばし、何かに阻まれた。
◆◆◆◆◆◆◆
「悪いが、その子はアタシの連れでね」
ソラだ。
騒ぎを聞きつけて来たのだろうか。剣の柄で男の腕を抑えている。
「まだこの子の話は終わっちゃいないよ」
ソラは知子に向かいニヤリと不敵な笑みを見せた。その目は『こいつらに聞かせてやれ』と知子を促しているようだ。
知子は頷き、ピコを胸の高さで軽く抱いた。
「ピコの運命はピコが決めるはず…人を襲うとは決まってない」
それは、知子が否定して目をそらした考えだ。
だが、知子は知子の意思でそれを口にする。
「運命は決まってない!」
その瞬間、ピコが淡く輝いた。
目を凝らさなければ見逃すような慎ましやかな光。だが、その光には見覚えがある。
「ソラ、ピコが…!」
「まさか、これは知恵の鳥?」
信じられないことに、産まれたばかりのピコが羽ばたいた。
知子がそっと手を放すと、ピコは1度だけ振り返り、空へと弱々しく飛び立った。
これには男たちもざわつき、声を出して驚いている。
「闇夜を昼に変える知恵の鳥……生育環境で姿が変わるのだろうか、それとも血鴉の幼体と似ているだけの別種なのか。環境で変わるとすれば何がきっかけなのだろう?不思議な鳥だ」
「不細工でふらふらしてる」
2人は顔を見合せクスリと笑った。
「トモ、アタシは運命はダイヤモンドと炭のようなものだと思う」
唐突なソラの言葉に知子は首をかしげた。これまでとは違い、優しい声色だ。
「科学の国では炭素を人工ダイヤモンドにできるのさ。高温高圧合成、化学気相蒸着、爆発合成、さまざまな方法で行われている」
ソラは知子にくっついていたピコの羽をつまみ上げ、夕日に透かすようにして観察した。
「黒い炭がダイヤモンドになるように、不細工な鳥が知恵の光を放つように、周囲の環境や関わった人によって運命は光り輝くものになるはずさ。アタシもトモとピコとの関りで新しい発見があった。それはとても素敵なことさ」
知子の手の平に、ソラはそっと羽を置いた。
「トモ、アンタは自分で1つの答えを出した。その答えが正しいか、変化するかは分からない。だけど、その気づきを大切にすれば人生はダイヤモンドになるはずさ」
知子はなんと答えていいのか分からず、曖昧に「うん」と頷いた。
いつの間にか薄暗くなった空にはもうピコの姿は見えない。
だが、2人はしばらく夜空を眺め続けた。
小説の続きを読む
新連載を読みたい方は、ぜひ以下のLINEにご登録ください。
ココロほっとLINEへの登録はこちら