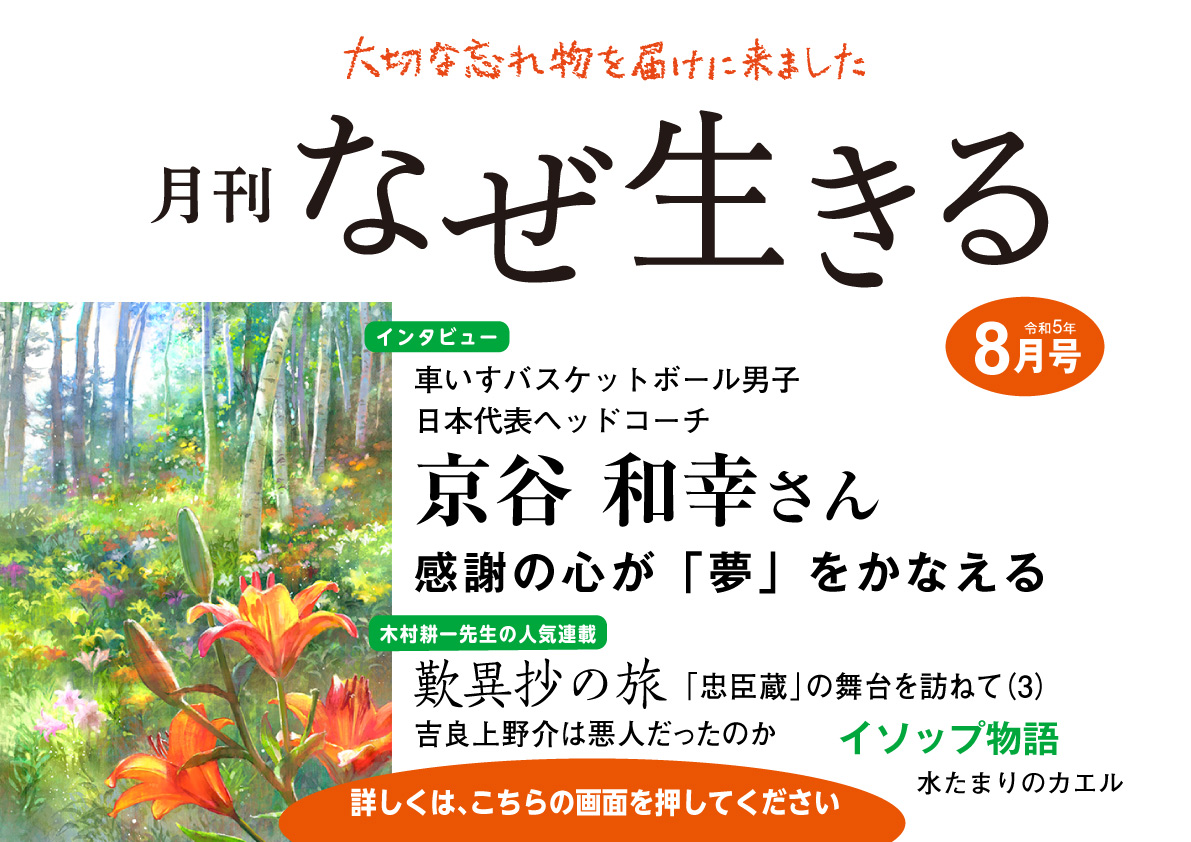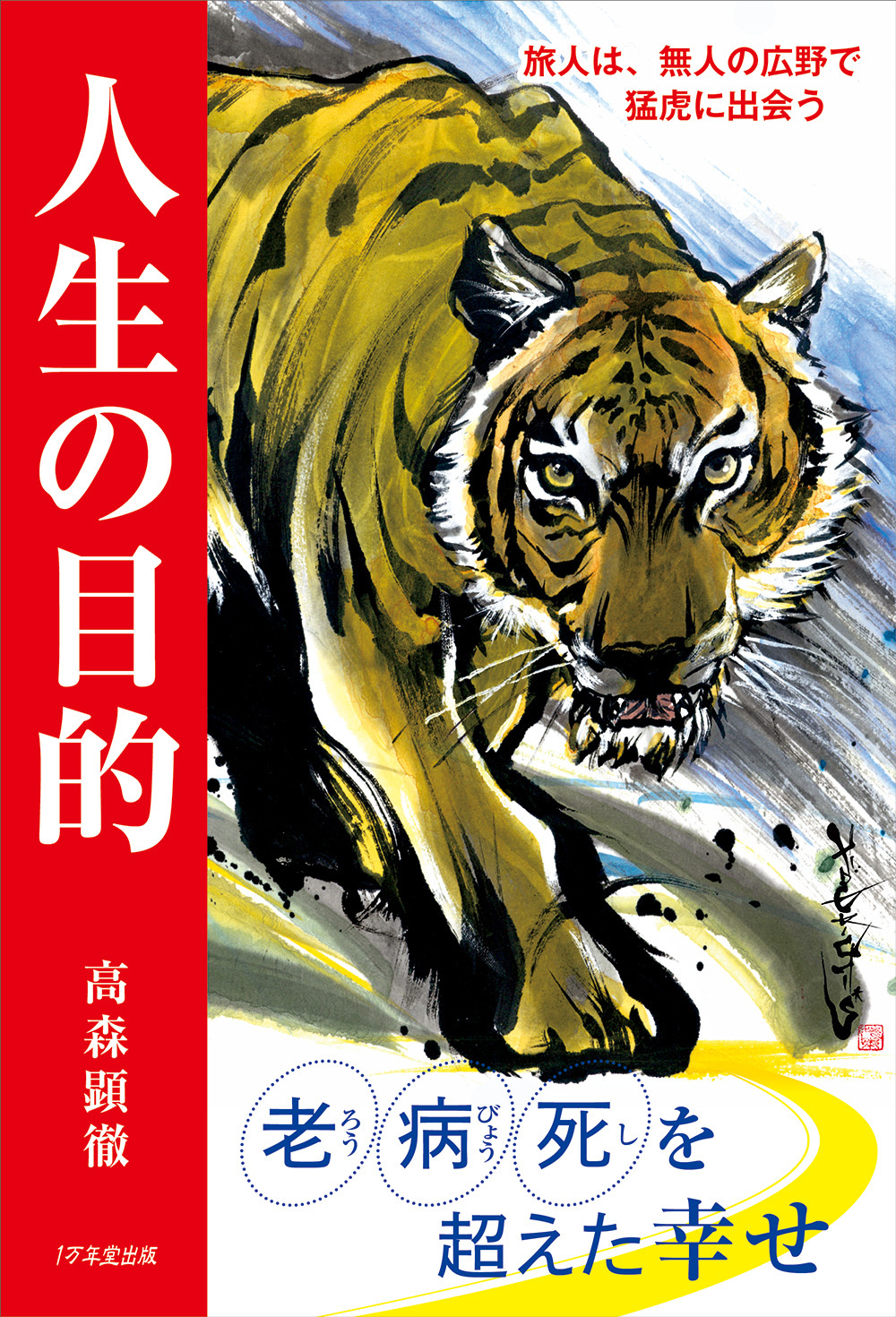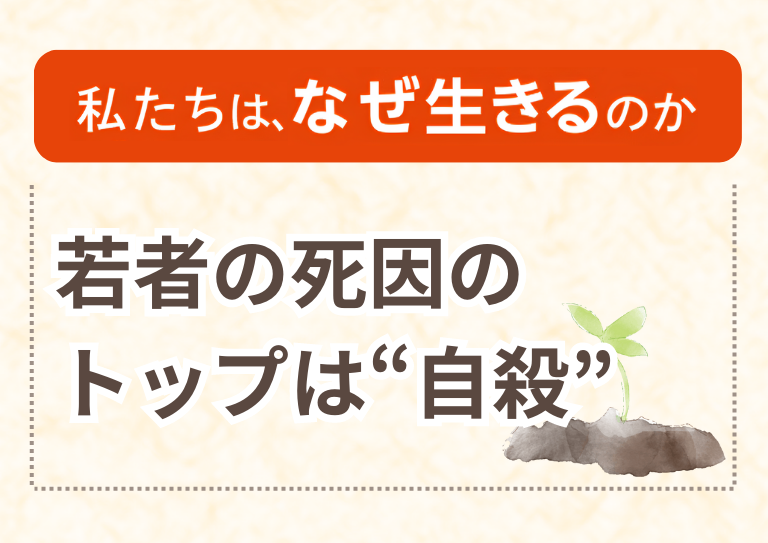
8月も後半になりました。
学校の夏休み明けが近付くこの時期、必ずニュースで話題になるのが、若い世代の自死の問題です。
そんな重い話……と避けてしまいがちな話題ですが、実は哲学的に考えると、「人間とは何か」を問い直すきっかけにもなるそうです。
哲学者・伊藤健太郎先生にその理由をお聞きしました。
人は、何のために生まれてきたのでしょうか。
どんなに苦しくとも、生きねばならぬ理由は何か。
「なぜ生きる」
これこそ最も大事な、いや、一刻も早く解決しなければならない問題なのです。
その重要性、緊急性を示すために、今日は、「自殺」について考えたいと思います。
若者の死因のトップは“自殺”
─じ、自殺ですか……? 始まったばかりですが、さっそく、暗い気持ちになってきました。
確かに自殺は、できれば考えたくない暗い悲劇でしょう。だからといって、目を背けることは許されません。
世界保健機関(WHO)の統計(2012年)によれば、世界における一年間の自殺者は約80万人です。40秒に1人が、自ら命を絶っていることになります。
日本人の死因の第一位はガンだとよくいわれますが、それは40歳以上の中高年のことであって、10代から30代までの若者は、自殺がトップです。

※ 厚生労働省「令和3年人口動態統計月報年計(概数)の概況」より作成
─10代から30代までの死因はトップが自殺……。初めて知りましたが、これは大変な問題ですね。
はい。これほど深刻な社会問題があるでしょうか。未来を担う子どもたちの命を守るのは、大人の責務です。
─うーん、でも、こんなに自殺する人が多いのは、やっぱり日本の社会に問題があるのではないでしょうか?
それが、日本だけの問題ではないのです。
アメリカには人口より多い数の銃があり、その規制が盛んに論じられています。
しかし銃を自分に向けて世を去った人は、銃で殺された人の二倍に上ることは、あまり知られていません。
人類の歴史においては、戦争と殺人で命を落とす人よりも、自殺者のほうが多いのです。
戦争や犯罪をなくすことも大切ですが、自殺をなくすことは、もっと尊い人助けであり、最大の人命救助といえるでしょう。
─日本だけでなく、世界中で大きな問題になっているのですね。哲学では、自殺について、どのように考えられているのでしょうか?
なぜ苦しくても、自殺してはいけないのか。哲学が論ずべき重要な問いは、これ一つだと、フランスの小説家、カミュは言います。
真に重大な哲学上の問題はひとつしかない。自殺ということだ。
人生が生きるに値するか否かを判断する、これが哲学の根本問題に答えることなのである。
(『シーシュポスの神話』カミュ(著)清水徹(訳)より)
自殺を防ぐには、その原因を取り除かなければなりません。
自ら死を選んだ人には、さまざまな事情があったのでしょう。しかしそこには、根本的な理由があるはずです。
生に絶望し、自分の意志で終わらせようとする生物は、人間だけだからです。
人間の特徴である「自殺」を、哲学的に分析してみましょう。
それによって「人間とは何か」が明らかになります。
(『月刊なぜ生きる』令和5年2月号「私たちは、なぜ生きるのか」より)
『月刊なぜ生きる』に好評連載中
伊藤健太郎先生、ありがとうございました。
初めはちょっと驚いてしまいましたが、自殺について考えるとは、人間に特有の行動を分析することなのですね。
たしかに、文化や国を超えて共通する、「人間とは何か」を掘り下げるヒントになりそうです。
伊藤健太郎先生の「私たちは、なぜ生きるのか」は、1万年堂出版の月刊誌『月刊なぜ生きる』で好評連載中です。
最新号の8月号の記事では、自分も相手も幸せになれる「利他(りた)」の効果について、解説されています。
試し読みは、コチラからどうぞ。
新刊『人生の目的』好評発売中!
新刊『人生の目的 旅人は、無人の広野で猛虎に出会う』が、今、全国の書店に並んでいます。
ロシアの文豪・トルストイが衝撃を受けた「ブッダの寓話」を解説しながら、カラーの墨絵も楽しめる一冊です。
新刊『人生の目的』の詳しい情報は、コチラからどうぞ。